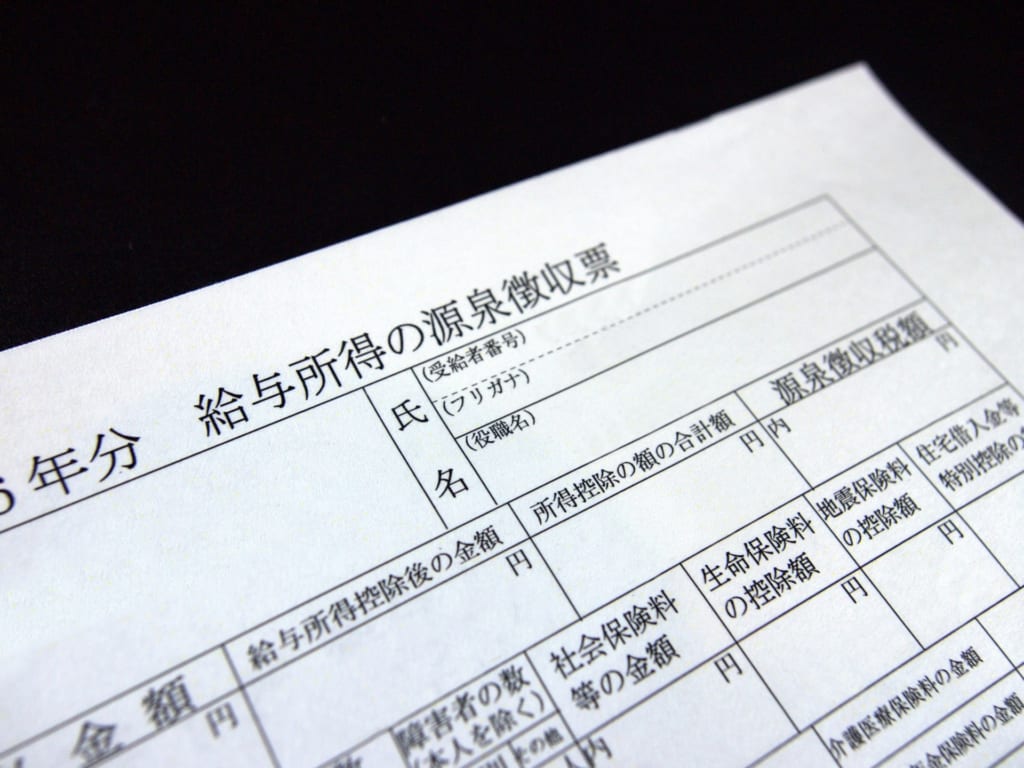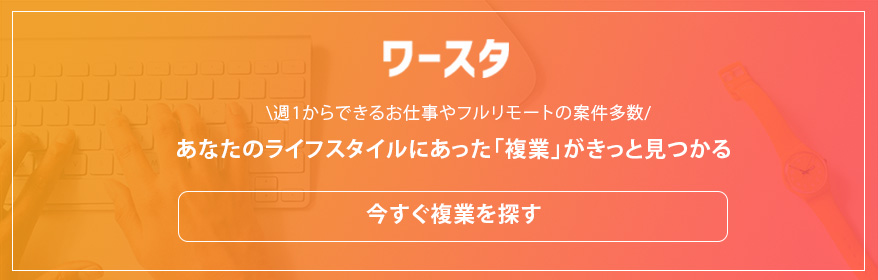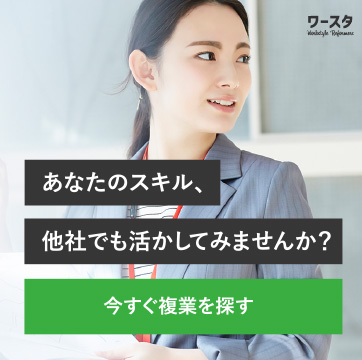あなたは源泉徴収についてどれほど理解できていますか?
複業してる方であれば「複業やフリーランスの場合、源泉徴収ってされるの?」と気になったことがあるのではないでしょうか。
そこで今回は、源泉徴収について詳しく解説します!
源泉徴収とは?
そもそも源泉徴収とは、給与や報酬を支払う事業者が、所得税を予め給与や報酬から差し引き、代理で納税する制度のことです。
また、事業者が給与や報酬を受け取る人から源泉徴収し、本人に代わって納める所得税を源泉所得税といいます。
源泉徴収制度は税務署の業務負担を減らすことができ、徴税制度の効率化を実現しています。
源泉徴収の対象になる業務(報酬や料金等のケース)
正社員の給与所得であれば源泉徴収の対象になることは間違いありません。
しかし、給与所得ではない複業やフリーランスで行っている業務でも、源泉徴収の対象となるケースがあります。
源泉徴収の対象となる業務は以下の通りです。
- 原稿料や講演料、デザイン料など
※ただし懸賞応募作品等の入選者に支払う賞金等については、一人に対して1回に支払う金額が5万円以下であれば、源泉徴収をしなくてもよいことになっています。
- 弁護士、公認会計士、司法書士等の特定の資格を持つ人などに支払う報酬・料金
- 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬
- プロ野球選手、プロサッカーの選手、プロテニスの選手、モデルや外交員などに支払う報酬・料金
- 映画、演劇、テレビジョン放送等の出演等の報酬・料金や芸能プロダクションを営む個人に支払う報酬・料金
- ホテル、旅館などで行われる宴会等において、客に対して接待等を行うことを業務とするいわゆるバンケットホステス・コンパニオンやバー、キャバレーなどに勤めるホステスなどに支払う報酬・料金
- プロ野球選手の契約金など、役務の提供を約することにより一時に支払う契約金
- 広告宣伝のための賞金や馬主に支払う競馬の賞金
また、謝礼・研究費・取材費・お車代のような文言が使われて「報酬」と明記されていなくとも、実質的に上記の「報酬」や「料金」の性質がある場合は源泉徴収の対象になります。
源泉徴収が必要な報酬・料金等について詳しくは、国税庁の「源泉徴収が必要な報酬・料金等とは」のページもご覧ください。
また、ライターへの報酬は原稿料にあたるため、源泉徴収が義務づけられています。
しかし源泉徴収し忘れる依頼主も少なくありません。
もし源泉徴収が行われずに報酬が振り込まれていた場合、ライター側で何かをする必要はありません。
源泉徴収した所得税を納めるのは依頼主の義務です。ライター側ではきちんと確定申告を行っていれば問題ありませんが、本来原稿料は源泉徴収されるべき対象のため事前に依頼主と源泉徴収について話し合っておきましょう。
源泉徴収の税額について
さて、源泉徴収されるものには「給与」の他に「報酬や料金等」もあることがわかりましたね。
実はどちらに分類されるかで、源泉徴収の税額が異なるのです。
給与にかかる源泉徴収の税額は「源泉徴収税額表」を見ればわかり、報酬や料金等にかかる源泉徴収税額は受け取った報酬や料金の金額から算出します。
給与にかかる源泉徴収税額の計算方法
源泉徴収税額表はいたってシンプルです。
社会保険料等を控除した給与の額面ごとに税額が決まっているので、対応した欄を確認するだけで税額がわかります。
ただしひとつ落とし穴があり、源泉徴収税額表には甲欄と乙欄があります。
2箇所以上から給与をもらっている場合は甲欄と乙欄の両方を使うことになるので、詳しくは「主たる給与と従たる給与の違い」をご覧ください。
報酬や料金にかかる源泉徴収税額の計算方法
報酬や料金には、基本的に以下の計算式で源泉徴収の税額を計算します。
- 同一人に対し1回に支払われる金額が100万円以下の場合、税額は支払われる金額の10.21%です。
:税額=(支払われる金額)×0.1021
- 同一人に対し1回に支払われる金額が100万円超の場合、税額は支払われる金額から100万円を引いた金額の20.42%と102,100円を足した金額です。
:税額=(支払われる金額-1,000,000)×0.2042+102,100
ここで気をつけたいのは、同一人に対し1回で支払われる金額とは何かということです。
国税庁が公表している法第205条では、「同一人に対し1回に支払われる金額」とは、同一人に対し1回に支払われるべき金額をいうと述べられています。
要するに、1つの契約ごとに支払われるべき金額ということです。
【計算例】
Case1:支払われる金額が50万円の場合
500,000×0.1021=51,050
Case2:支払われる金額が150万円の場合
(1,500,000-1,000,000)×0.2042+102,100=204,200
ただし、例外もあります。以下の場合の税額は100万円を超えた場合の規定は適用されず、支払われる金額から一定の金額を差し引いた金額に所得税率の10.21%がかかります。
- 司法書士等の税額は、支払われる金額から1万円を差し引いた残額の10.21%です。
- 外交官等の税額は、報酬・料金の額から1か月当たり12万円(同月中に給与等を支給する場合には、この12万円からその月中に支払われる給与等の額を控除した残額)を差し引いた残額の10.21%です。
- ホステス等の税額は、報酬・料金の額から同一人に対し1回に支払われる金額について、5千円にその報酬・料金の「計算期間の日数」を乗じて計算した金額(同月中に給与等の支払がある場合には、その計算した金額からその計算期間の給与等の支給額を控除した金額)を差し引いた残額の10.21%です。
※この「計算期間の日数」とは、「営業日数」又は「出勤日数」ではなく、ホステス報酬の支払金額の計算の基礎となった期間の初日から末日までの全日数です。
- 広告宣伝費の賞金等の税額は、賞金の額から50万円を差し引いた残額の10.21%です。
個人事業主や複業・副業をしている人の源泉徴収
ではここから、複業をしている人の源泉徴収について解説します。
主たる給与、従たる給与の違い
本業だけでなく複業もアルバイト・パートなどの給与所得に該当する場合、給与を「主たる給与」と「従たる給与」に分類して源泉徴収税を計算しなければいけません。
どちらに当てはまるかで源泉徴収される税額が異なり、同じ給与額で比べると主たる給与より従たる給与の方が税額が高く設定されているのです。
先程説明した源泉徴収税額表で、主たる給与であれば甲欄、従たる給与であれば乙欄を見れば税額がわかります。
では主たる給与と従たる給与の分類方法ついて説明します。
- 主たる給与:一般的には本業の給与で、1年間に稼いだ給与や勤務時間の比重が一番重いものが該当します。
また主たる給与の勤務先には「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」をはじめとする年末調整の書類を提出して給与控除を受けることが可能です。
- 従たる給与:本業よりも給与や報酬の額、勤務時間の比重が軽いものが該当します。従たる給与の勤務先では年末調整は受けられません。
2箇所以上で勤務している場合はどちらを主たる給与に設定してもよいのですが、前述のように従たる給与の方が税額が高いです。
年末調整の書類を提出した勤務先が主たる給与の扱いになるので、稼いだ給与額が多い勤務先を主たる給与の会社に選択するとおトクでしょう。
報酬や料金を源泉徴収をされる際の注意点
源泉徴収をされたときは、どんなことに注意すればよいのでしょうか。
以下に挙げる項目について注意しましょう。
源泉徴収と支払調書の違い
源泉徴収と支払調書はどちらも給与や報酬が記載された書類なので似ていますが、役割が違います。
源泉徴収票は雇用契約を結んでいる労働者がいる会社が発行するもので、労働者にも税務署にも提出しなければいけません。
一方で、支払調書は会社が「誰に対してどのような業務内容を依頼し、いくら支払ったか」を税務署に報告するための書類で、労働者へ支払調書を提出する義務はないのです。
しかし、複業をしている方やフリーランスの方は支払調書を受け取っておくことで、いくら源泉徴収されたかを明確にできるメリットがあります。
もし支払調書を受け取りたいのであれば、契約を結ぶ前に相手方に頼んでおくと良いでしょう。
もしくは、普段からしっかり帳簿をつけて請求額や源泉徴収額を記入しておけば支払調書がなくても確定申告の時期に慌てる必要がありません。
請求書の消費税
作成する請求書では、消費税の扱いに注意しましょう。
消費税の表記には、以下の2つがあります。
- 内税表記
:請求書に特別な記載がない表記です。消費税も含む報酬・料金として支払われる金額の全部が源泉徴収の対象となります。
- 外税表記
:請求書で報酬の金額と消費税の金額を明確に分ける表記です。消費税の金額を除いた報酬の額のみを源泉徴収の対象とすることができます。
一見同じ報酬額でも、外税表記の方が課税の対象になる金額が抑えられるので、分けられる場合は分けて記載しましょう。
【具体例】
- 請求書に税込み報酬6万と記載するケース(内税表記)
:源泉徴収額は、報酬6万円の10.21%に該当する6,126円になります。
- 請求書に税抜き報酬5万4,546円、消費税5,454円と記載するケース(外税表記)
:こちらでは報酬額と消費税額が分けてありますね。
源泉徴収額は5万円の10.21%に該当する5,569円になります。
請求する金額が同じ6万円でも、消費税を区別して記載すれば約550円分の節税になります。
還付申告は遡れる
あなたが本来納めるべき額より多くの額を納税していた場合、過剰分を返還してもらう「還付申告」ができます。
還付申告の期間は申告をする年分の翌年1月1日から5年間です。
もし、これまでに還付申告をしていない人は、今年(令和2年)の12月31日までは平成27年分まで遡って申告できます。
還付申告の方法は通常の確定申告と同様の手段で行います。
しかし還付申告の場合は確定申告の期限である3月15日以降も申告ができるので、今一度税金を納めすぎていないか確認してみてはいかがでしょうか。
源泉徴収票を紛失・もらい忘れてしまった場合
複業をしていて確定申告をする人は源泉徴収票は必須です。
しかし中には、源泉徴収票をうっかり紛失したり、もらい忘れてしまった人もいるのではないでしょうか。
そんな場合は、発行元の会社に再発行を頼むことができます。
万が一、相手方が再発行に応じてくれないときは、「源泉徴収票不交付の届出書」という書類を税務署に提出したり、拒否された理由を明らかにして直接税務署に相談するといった手段もあります。
あなたも源泉徴収義務者かも?!
源泉徴収を行わなくてはならない人のことを「源泉徴収義務者」と呼びます。
あなたがたとえ個人事業主だとしても、人を雇って給与を支払っていたり、源泉徴収の対象となる業務で報酬を支払っていたりする場合は源泉徴収を行う必要があります。
例外として、従業員を1人も雇っていない場合や、弁護士や税理士だけに報酬や料金を払った場合は、源泉徴収する必要はありません。
また常時2人以下の家事使用人だけに給与・退職金を支払っている場合も、源泉徴収を行う必要はありません。
源泉所得税の納付方法
源泉徴収義務者である事業主は源泉徴収した所得税を国に納める必要があります。
通常であれば給与や報酬・料金を支払った月の翌月10日までに以下のどちらかの場所に納税します。
- 管轄の税務署
- 金融機関
ただし、納税については特例があります。
「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請」を行い、適用された事業者は年2回にまとめて納税することができます。
この場合、以下の期日までに納税する必要があります。
- 1月から6月までに支払った所得から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税:7月10日
- 7月から12月までに支払った所得から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税:翌年1月20日
申請は給与支払事務所等の所在地の所轄税務署へ申請書を持参するか郵送で行うことができます。
しかし、特例は全ての事業主に適用されるわけではありません。
対象者は従業員数が常時10人未満である源泉徴収義務者です。
この特例を受けていて、もし従業員数が10人以上になった場合には要件から外れることになるため、速やかに税務署に届け出ましょう。
また、期日までに納税していないと「延滞税」と「不納付加算税」という罰金が課されるので気をつけましょう。
源泉所得税の納付に必要な書類は?
従業員の給与や税理士、弁護士など専門家への支払いに関しては、「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書」という納付書を利用します。
その他、原稿料やデザイン料などの報酬に関しては、「報酬・料金等の所得税徴収高計算書」を利用します。
また、年2回にまとめて納税する特例を受けている場合と、特例を受けていない場合とで納付書の用紙が違うので注意してください。
特例を受けている場合は「納期特例分」で、翌月納付の場合は「一般分」となります。
納付書の必要事項を全て記入したら、管轄の事務所もしくは金融機関に提出しましょう。
現在では管轄の事務所や金融機関に行かずとも、e-Taxで納付申告からインターネットバンキングを利用して納税ができます。
あなたの会社の社員が複業をしているときの対応
今までとは少し視点を変えて考えてみます。
あなたが会社の経理担当で、会社自体は複業を禁止していない場合、社員の複業に関して注意しなければならないことは何でしょうか。
3つのパターンに分けて紹介します。
給与所得以外の所得で複業を行っている社員がいる場合
複業をしていない社員と同様の対応で問題ありません。
所得税については自社で年末調整を行い、源泉徴収票を発行すれば、従業員がそれをもとに確定申告を行いますし、自社で社会保険に加入していれば個人事業を営んでいても新たに加入する必要はありません。
社員のことを考えると、確定申告のやり方などについての情報を共有してあげてもよいでしょう。
複業でも給与所得を受け取っている社員がいる場合(自社が主たる給与)
本業として自社に勤務しているなら、複業をしていない社員と同様の対応で問題ありません。
年末調整を行って源泉徴収票を発行すれば、社員は他の会社でも発行してもらった源泉徴収票をもとに確定申告を行います。
社会保険については、複業先で社会保険の加入義務が発生した場合、社員自身で年金事務所に「健康保険・厚生年金保険所属選択・二以上事業所勤務届」を提出する必要があります。
先程の確定申告と同様に、社会保険の手続きを教えてあげるとよいですね。
別の会社が本業で給与所得を受け取っている社員がいる場合(自社が従たる給与)
自社が複業で、別の会社が本業の場合はいくつか注意することがあります。
別の会社が本業の場合は、あなたの会社では年末調整をする必要はない代わりに、その社員に「源泉徴収票」を発行する義務があります。徴収する税額は前述の通り、「乙欄」のものです。
また、これも既出ですが年末調整の書類の提出は1社しかできません。
万が一「扶養控除等(異動)申告書」の提出を受けた場合は、他社で提出していないかどうか確認しましょう。
社会保険料については自社が本業である場合と同様なので、年金事務所へ「健康保険・厚生年金保険所属選択・二以上事業所勤務届」を提出する必要があることを伝えてあげましょう。
さいごに
さて、フリーランスや複業をしている際の源泉徴収について理解いただけたでしょうか。
給与所得でなくても源泉徴収される業務があることや、源泉徴収の税額の計算方法など知識として持っておくことは大事です。
確定申告を行うことで税金が還付される可能性もあるため、損をすることのないよう源泉徴収を正しく理解しておきましょう。
今すぐ複業をさがす